2026年2月20日 07時46分
[南宇和高校]
2月19日、「南宇和高校教育振興協議会活動報告会」が開かれました。


愛南町長様をはじめ多くの皆さまに出席をしていただき、心から感謝いたします。
- 次世代リーダー養成塾
- 総合的な探究の時間(地域未来探究)
- ボランティア活動
- 地域人材育成事業(地域振興研究部)
- 海外研修
- 全国大会出場
上記内容に関しての報告が行われました。








すべての報告が大変すばらしく、このような充実した活動が実施できたことは教育振興協議会の皆さまのおかげです。最後に中村愛南町長から挨拶をいただきましたが、「もっと話を聞きたかった。来年度は時間を長くしてください。」と言っていただけるほど、生徒たちの活動報告は参加していただいた皆さんに届いたと思います。


南宇和高校、最大の魅力は生徒たちです。これからもこの学校、そしてこの町で夢や目標に向かいチャレンジできる学校であり続けます。引き続き本校の教育活動に対し温かい目で目守っていただけると幸いです。参加してくださった皆さま、本当にありがとうございました。
高山保育園の園児7名と野村高校畜産科1年生で動物ふれあい体験を実施しました。最初はウサギを怖がる様子もありましたが、最後にはだっこをしながら可愛がるようになりました。園児の成長に驚くばかりです。畜産科1年生も園児達との関わりが自然とできるようになってきました。来年度からの活動に期待です。



2026年2月18日 09時00分
[北宇和高校三間分校]
2月15日(日)に開催された「第33回宇和島市産業まつり」に、今年も北宇和高校三間分校 地域情報ビジネス部が出店しました。
当日は、多くのお客様でにぎわい、「MIMAライスバーガー」も無事に完売することができました。お立ち寄りいただいた皆さま、ありがとうございました。
これからも地域を元気にしていけるよう取り組んでいきますので、応援よろしくお願いしま~す。

(当日は3年生も応援に来てくれて、心強い一日となりました!)
2026年2月13日 07時01分
[南宇和高校]
2/12(木)、御荘文化センターで本校の総合的な探究の時間最終発表会が行われました。
本校では、総合的な探究の時間に農林、水産、文化・商工観光、防災・まちづくり、地域医療・教育・福祉の5分野に分かれて探究を行っています。それぞれの分野で代表になった班が、1年間の研究の成果を発表しました。
農林 生産分野「肥料の違いによってできる作物にどのような違いがでるか」
加工分野「愛南ゴールドで愛南町を盛り上げたい!!」
水産 「愛南ゴールド抽出液の水産分野への活用可能性の検討」
文化・商工観光 「愛南町宣伝隊」
防災・まちづくり 「NEW避難訓練2025」
地域医療・教育・福祉 「高齢者の食事改善」
最後に今年度の海外研修の報告も行われ、カナダでの研修での発見やそこで学んだことについて発表しました。
コンソーシアム委員の方々に5つの発表を審査していただき、地域医療・教育・福祉分野の 「高齢者の食事改善」が審査員特別賞に輝きました。どの班も、1年間の探究活動の集大成として、自らの学びを自信をもって発表しました。また、代表班以外の班も1年間を通して地域の課題に本気で向き合い、挑戦することができました。今後も地域での学びを大切にしながら、さらに探究を深めていきます。本日の模様は後日CATVにて放送されます。ぜひご覧ください。

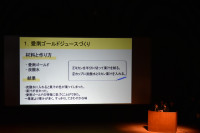

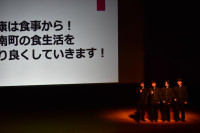



2026年2月12日 12時08分
[松山中央高校]
令和8年2月10日(火)に、松山中央高校にて、県立学校振興計画推進事業における令和7年度「進学指導研究推進プログラム」第2回公開授業を実施しました。
2時限目の「英語コミュニケーションⅡ」では、2年英語系クラスにて「江戸時代におけるリサイクリング業」を題材に、「歴史総合」との教科横断型授業を実施しました。江戸時代の循環型社会を支えた江戸の社会や当時の時代背景を学び、生徒は、当時のユニークなリサイクリング業について調べて、英語でプレゼンテーションを行いました。その中で、いかに江戸の人々が物を大切にして、ごみを出さない暮らしの工夫を行っていたのかを知りました。また、そこから得た知識を現代社会と結び付けて、今を生きる私たちが循環型社会実現のために何をすればいいのか、英語で考えて発信することができました。




3時間目の「公共」では、2年医療看護系クラスにて「マイクロプラスチック問題」を題材に、「生物基礎」との教科横断型授業を実施しました。重信川や瀬戸内海での現地調査や潮流図等の資料、カタクチイワシの胃の内容物の確認など、プラスチックごみの現況を、理科的視点で確認し、法律・経済学など公共的視点も併せて、問題の解決に向けて考察しました。




2026年2月12日 10時38分
[宇和島南中等教育学校]
本校生徒3名が「予土あす青春18プロジェクト 第3回高校生シンポジウム」に参加しました。
このシンポジウムは、JR予土線沿線エリアの高校生が、愛媛県・高知県をまたいで連携しながら沿線地域を盛り上げていくことを目的として行われており、本校は第1回から継続して参加しています。今回は松野町での開催となりました。午前中は、現地ガイドや高校生ガイドの案内のもと、4つのコースに分かれてまちあるきを実施しました。地域の歴史や文化、沿線ならではの魅力に触れながら理解を深めました。午後は、各校・団体がJR予土線に関する取組を発表した後、4つの班に分かれてディスカッションを行いました。予土線を生かし、松野町をどのように活性化できるかについて各班とも活発に意見を交わしました。大人だけでなく、大学生、同年代の高校生、さらには小学生まで、多くの世代が沿線活性化に向けて活動していることを知り、本校生徒にとって大きな刺激となりました。今回のシンポジウムは、生徒たちが自分たちの研究を続ける意義を改めて実感できる、貴重な学びの機会となりました。




総合的な探究の時間・教育班は、2月7日(土)に開催された「第10回 地域教育実践 南予ブロック集会」に参加しました。本校は事例発表として、ポスターセッション形式でこれまでの活動内容を報告しました。南宇和高校からは、愛南町の教育のこれからについて、高校生の視点で考えた提案を発表しました。
愛南町では今年、6か月健診を受けた赤ちゃんが45人でした。現在13校ある公立小中学校は、今後どのように変化していくのでしょうか。教育班では、この問いをもとに、将来の学校のあり方について検討しました。
その中でも、次の3つの観点について発表しました。
1つ目は、「教育水準が高い愛南町の学校」です。海外の学校事例を参考に、課題の在り方やICT機器を効果的に活用した学びの可能性について提案しました。
2つ目は、「この町でしかできない部活動・クラブ」です。小・中・高の連携を生かし、「防災地理部」や「お遍路部」など、地域の魅力を守り、伝統を次世代へ継承する取り組みを提案しました。
3つ目は、「合言葉はALL!」です。愛南町全体をフィールドとし、受け身ではなく、主体的・創造的に学ぶ教育の姿を描きました。
ポスターセッション終了後には、防災教育ワークショップや平城貝塚の見学も行いました。今回の集会で得た学びを、今後の探究活動や研究に生かしていきたいと考えています。
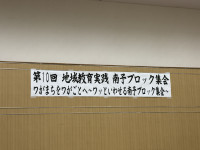

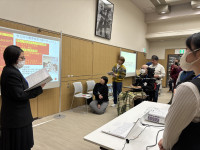



2026年2月9日 09時56分
[西条農業高校]




DXハイスクールの指定を受け2年目となる本校。環境工学科でも、デジタル技術を少しずつ取り入れています。今回は、これまで環境工学科では使う機会がなかったレーザー加工機で、竹に文字を入れてみました。とてもきれいに仕上がり、新しいものづくりの形が見えてきました。来年度は2年生の「農業情報活用」の授業で、さらに活動を広げていく予定です。